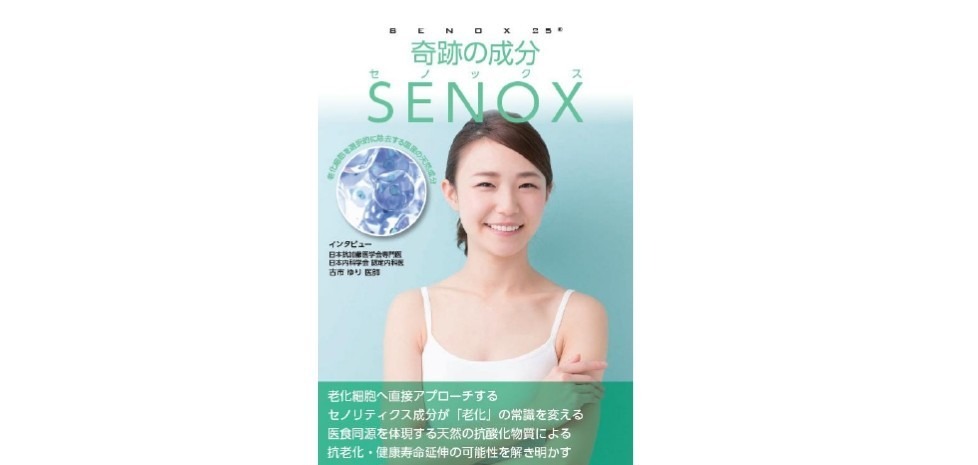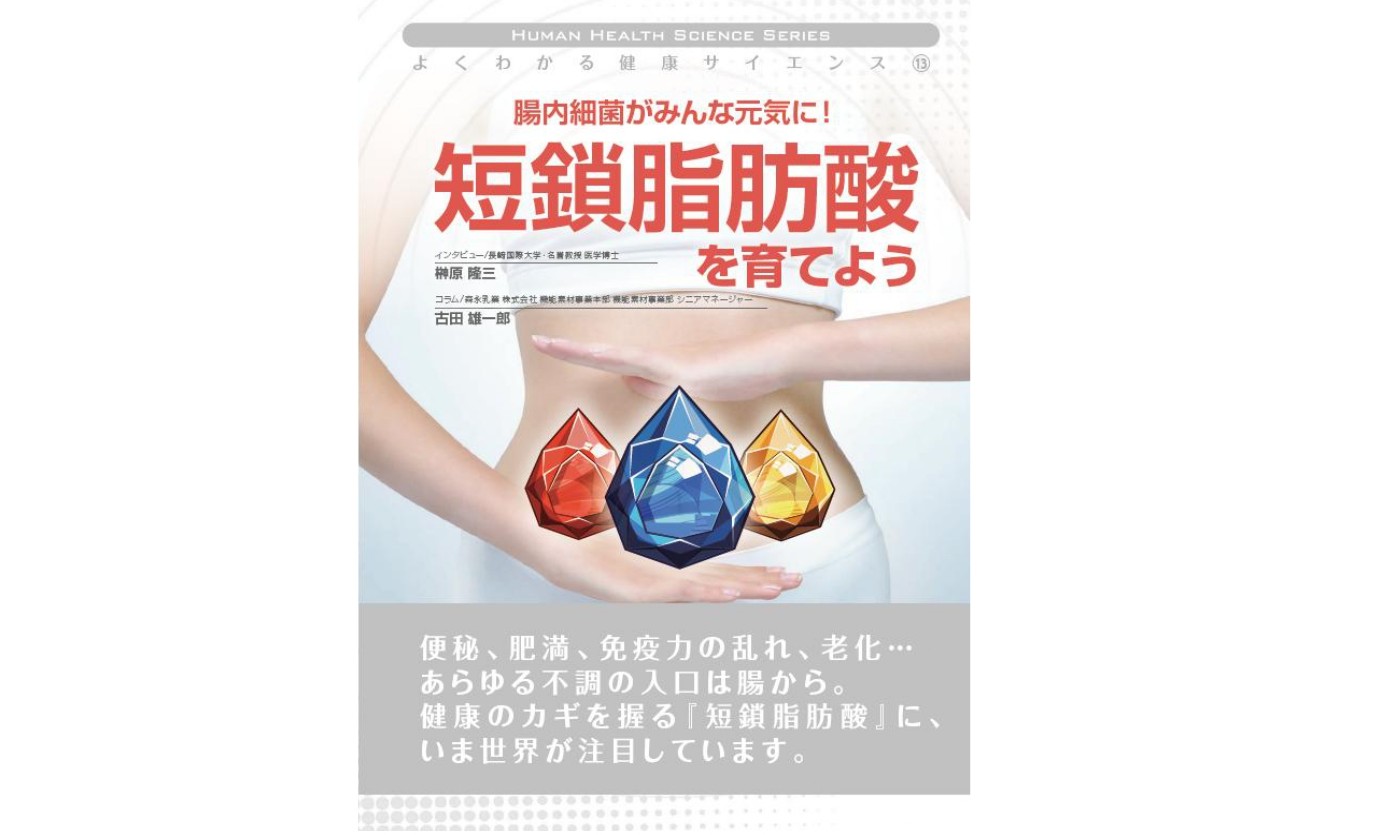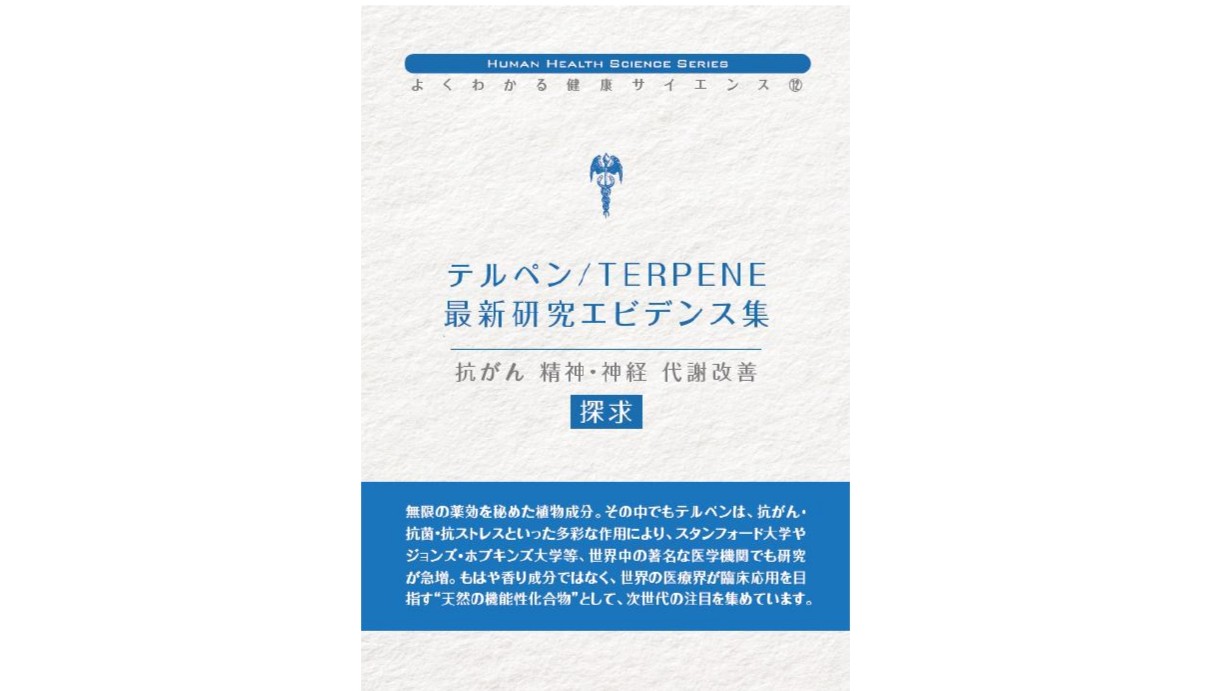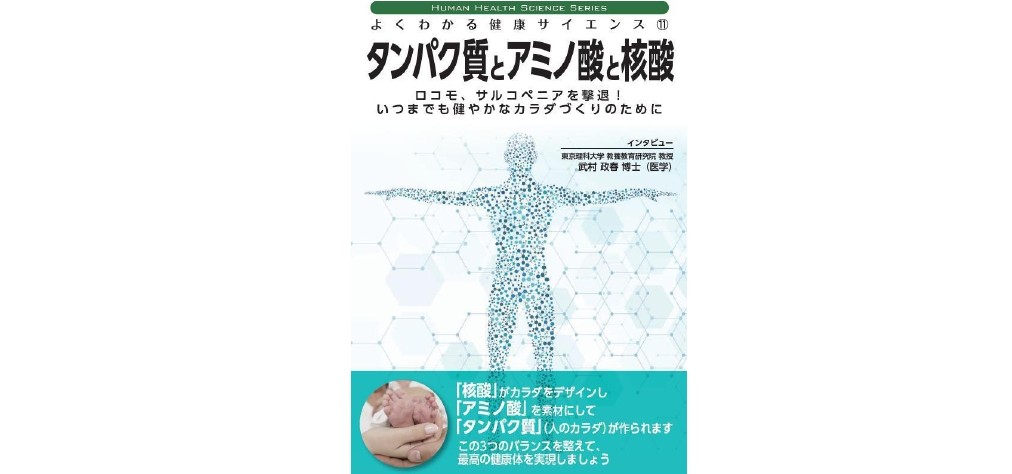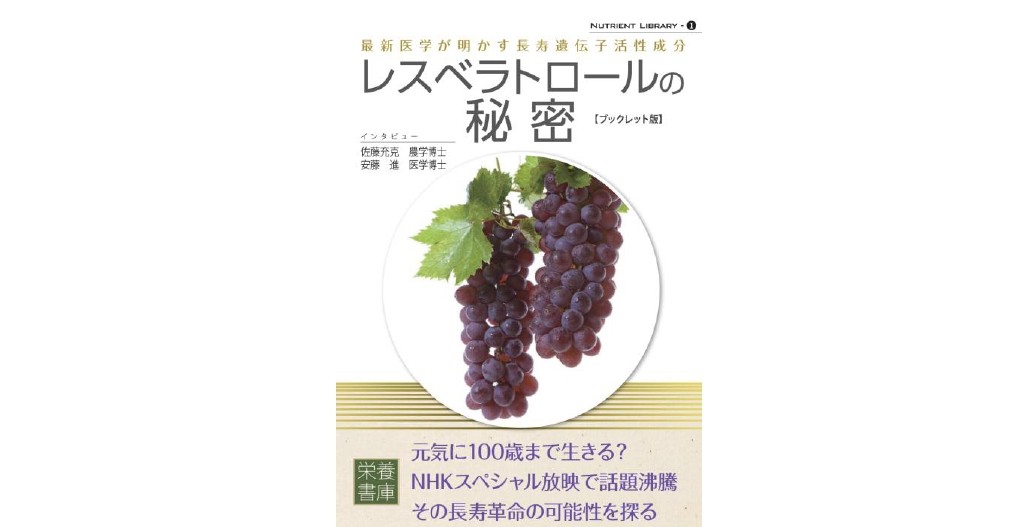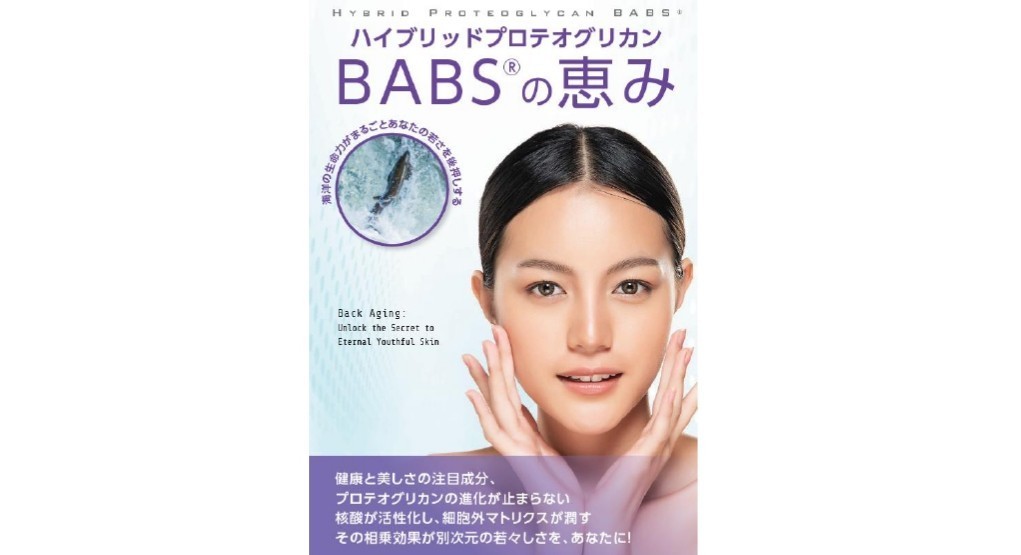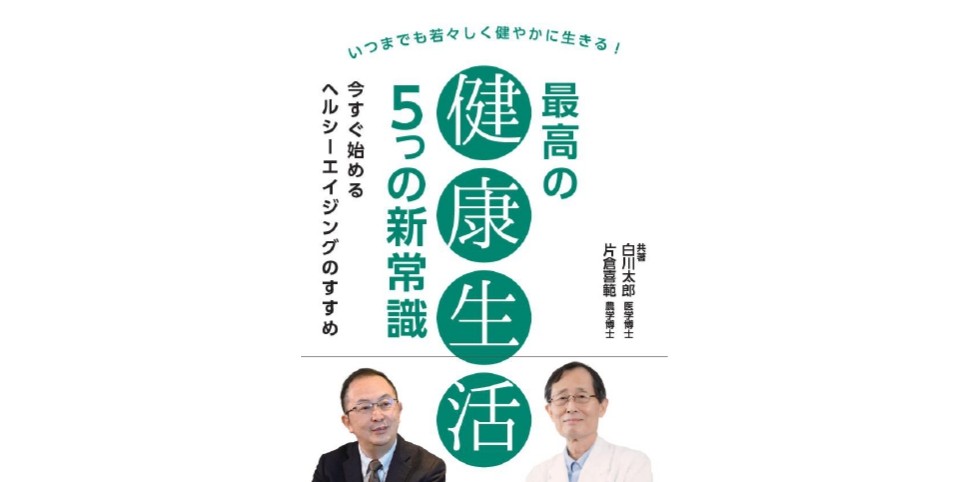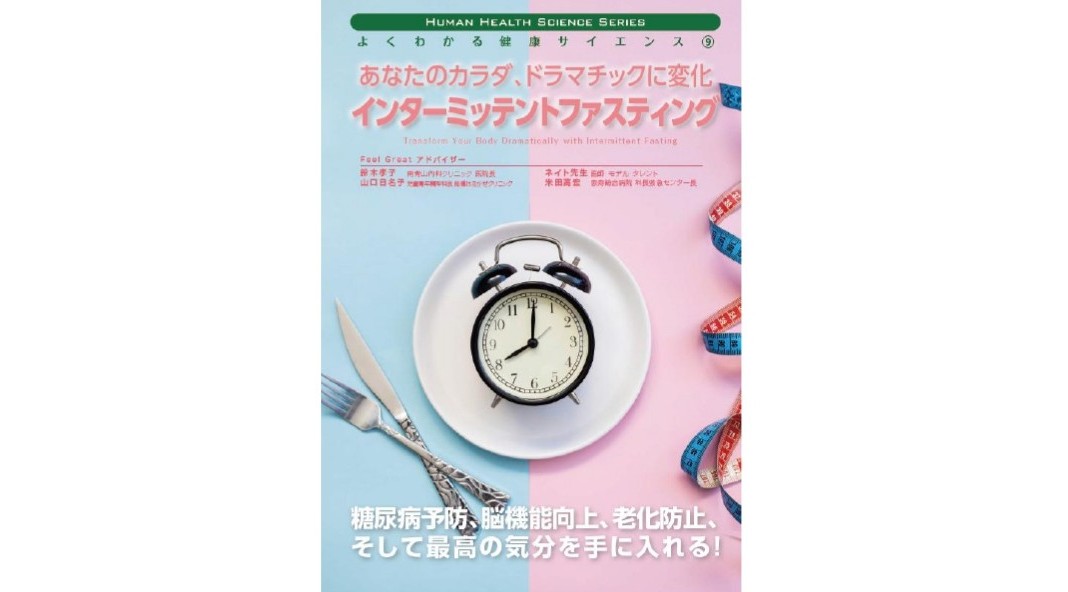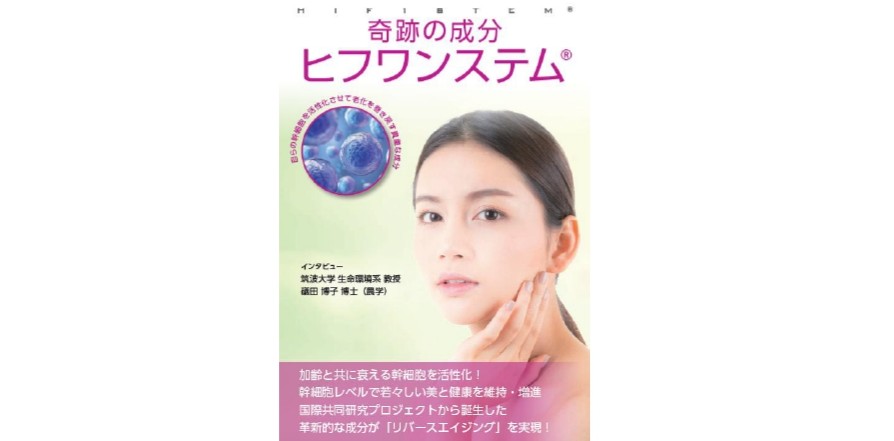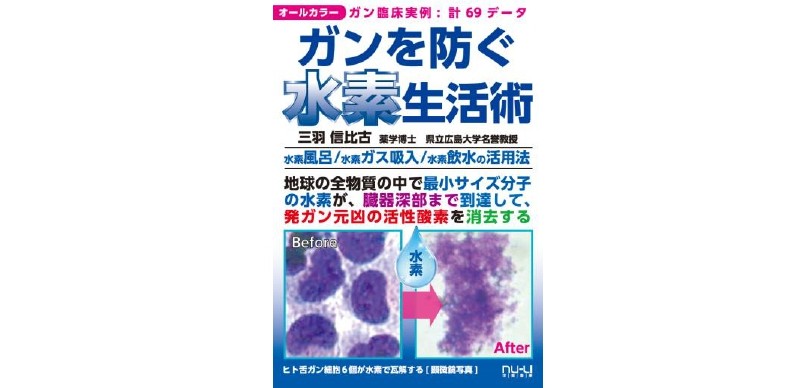脳と腸の関係
「腹が立つ」「腸(はらわた)が煮えくり返る」
私たちは、昔から心と内臓、特に腸の状態が密接に関係していることを、経験的に知っていました。嬉しい時にはお腹がすくし、緊張するとお腹が痛くなる。これらは、単なる気のせいではなく、実は「脳腸相関」と呼ばれる、脳と腸の間の双方向のコミュニケーションによって起こる現象なのです※。
腸は自ら情報を発信、脳の働きに影響を与えている
近年、この脳腸相関が、私たちの心身の健康に想像以上に大きな影響を与えていることが、科学的研究によって明らかになってきました。かつて、脳は体全体の司令塔であり、腸は単なる消化器官と考えられていましたが、実はそう単純ではありません。腸は、脳からの指令を受け取るだけでなく、自らも情報を発信し、脳の働きに影響を与えているのです。

ストレスにさらされて消化管の動きが止まる
この驚くべき脳と腸の対話は、どのようにして行われているのでしょうか? そのメカニズムを解き明かす研究は、実は20世紀初頭から始まっていました。当時、生理学者のウォルター・キャノンは、動物が強いストレスにさらされると、消化管の動きが止まってしまうことを発見しました。これは、危険な状況に直面した時に、消化よりも「闘うか逃げるか」の反応を優先させるための、体の防御メカニズムと考えられています。
ストレスと消化器の病気の関係
その後、ストレスと胃潰瘍や十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群といった消化器の病気との関係が詳しく調べられ、精神的なストレスが腸の機能に悪影響を与えることが明らかになりました。しかし、これらの研究は、主に脳から腸への一方通行の影響に注目したものでした。
腸内細菌が体の働きに関わっている
脳腸相関の研究に新たな風を吹き込んだのは、20世紀後半から急速に進歩した腸内細菌の研究です。先に紹介したように、私たちの腸の中には無数の細菌が、まるで一つの生態系のように共生しています(腸内フローラ)。
遺伝子解析技術の発展により、腸内フローラを構成する細菌の種類や、それぞれの細菌が持つ遺伝子の特徴を、網羅的に調べることが可能になりました。その結果、腸内細菌は、単に食べ物のカスを処理するだけでなく、私たちの体の様々な働きに関わっていることが明らかになったのです。

腸内細菌が短鎖脂肪酸を作り出す
腸内細菌は、私たちが消化できない食物繊維などを分解し、短鎖脂肪酸と呼ばれる物質を作り出します。この短鎖脂肪酸は、腸の細胞のエネルギー源となるだけでなく、血液を介して全身を巡り、様々な良い効果をもたらします。例えば、免疫細胞を活性化したり、炎症を抑えたり、さらには脳の働きにも影響を与えることがわかってきました。
※ Cryan, J. F., & Dinan, T. G. “Mind-altering microorganisms: the impact of the gutmicrobiota on brain and behaviour.” Nature reviews neuroscience 13.10 (2012): 701-712. DOI: 10.1038/nrn3346
『最高の健康生活 5つの新常識』より