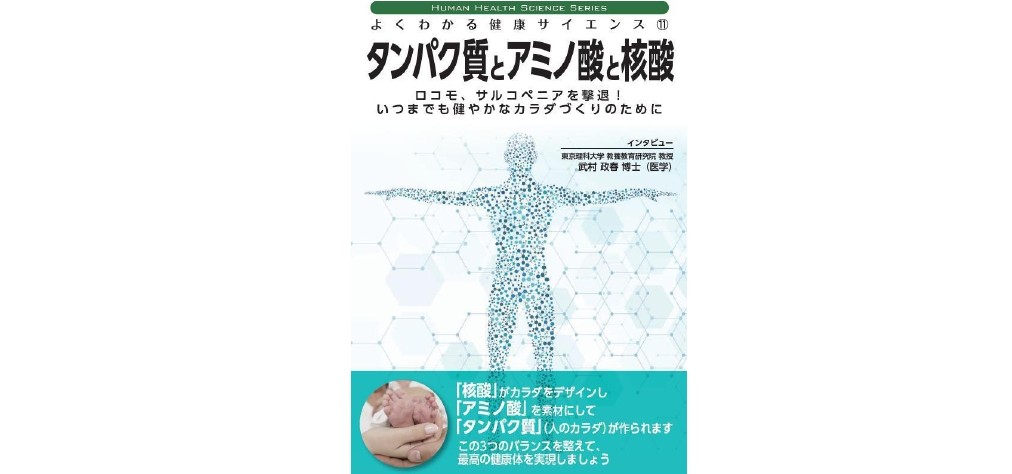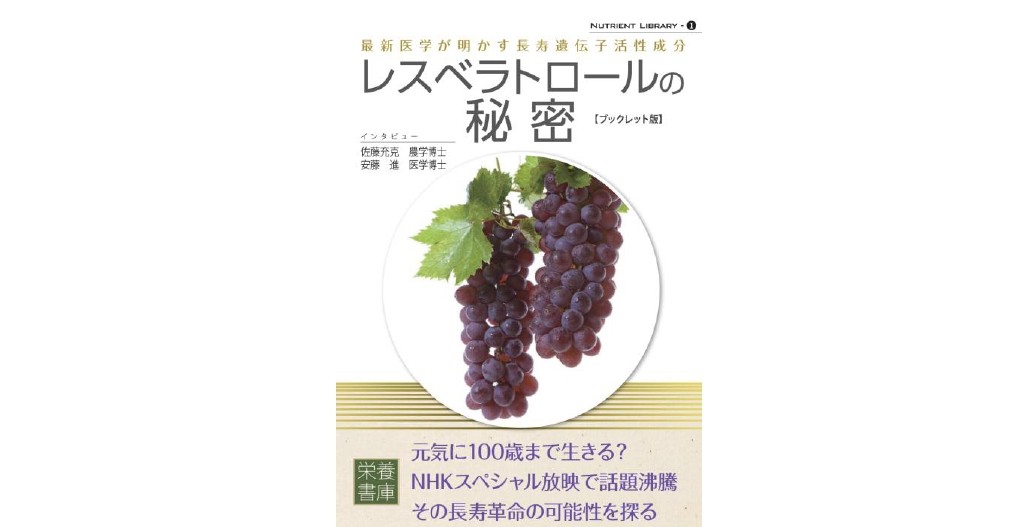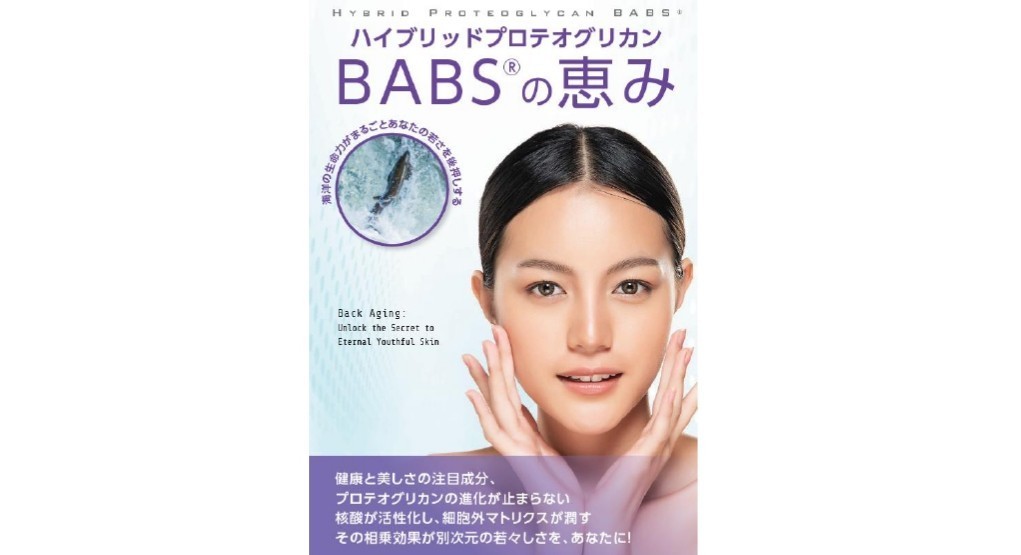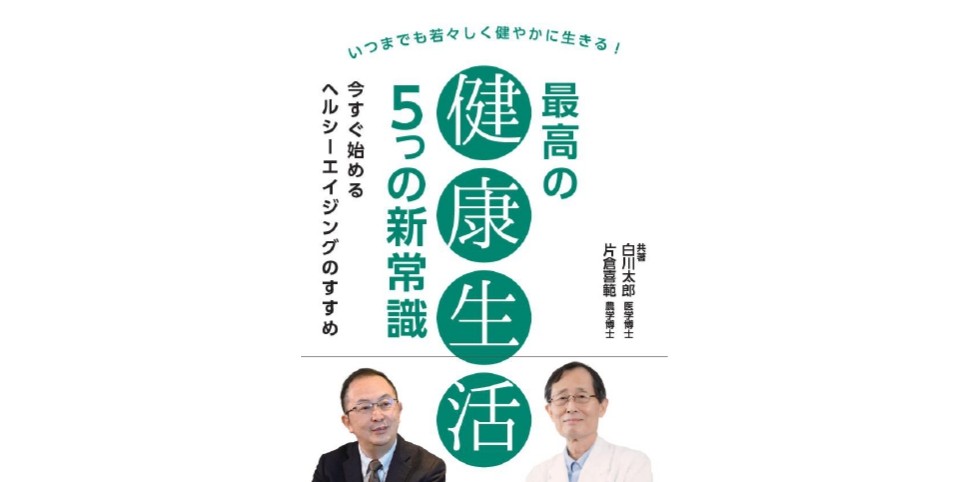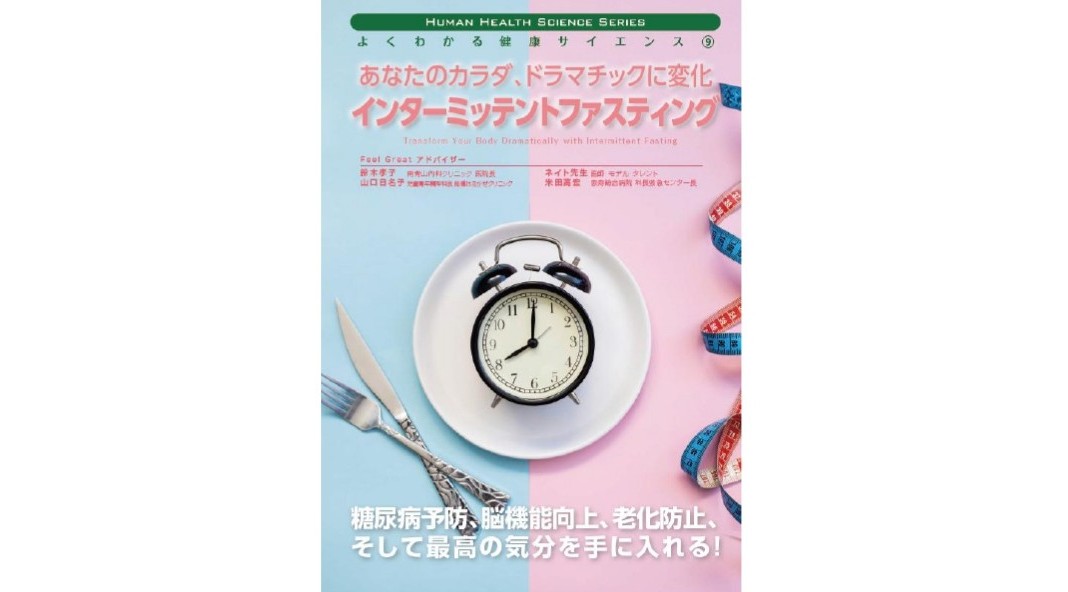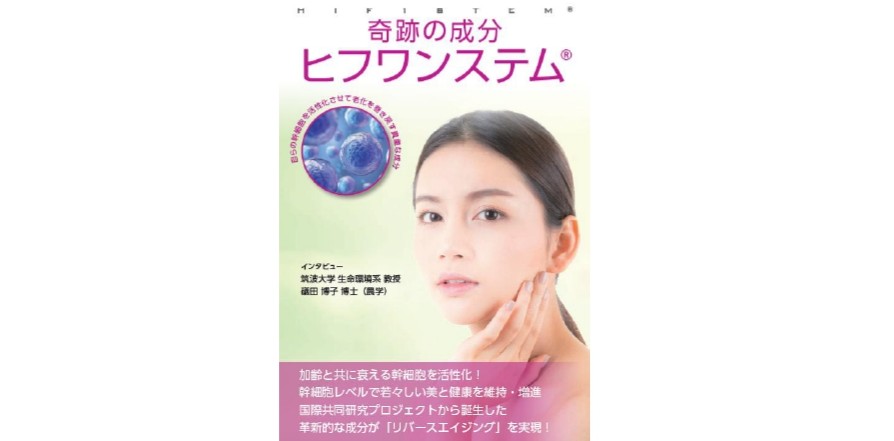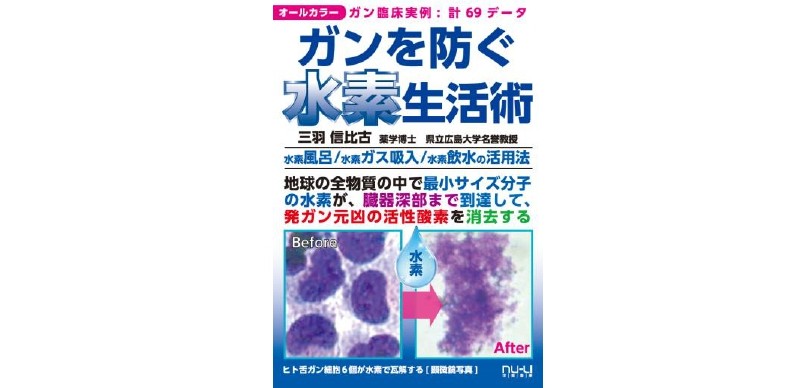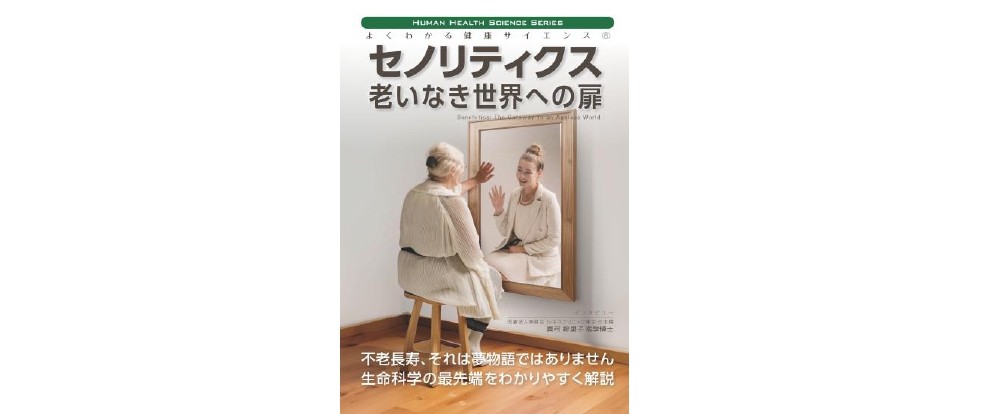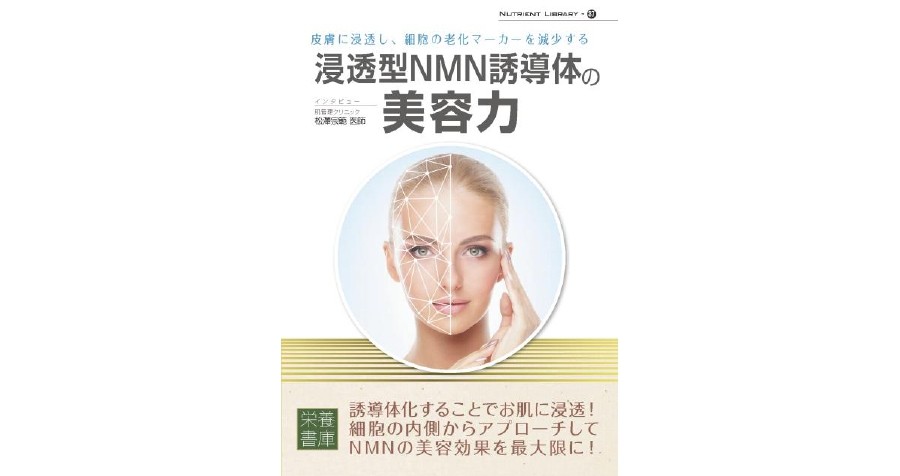東京理科大学 教養教育研究院 大学院理学研究科 教授
武村 政春 医学博士

タンパク質には筋肉づくり以外にも多種多様な働きがある
タンパク質は、主に筋肉を構成するイメージが強いですが、皮膚や髪、爪の素材となるケラチン、関節や肌の弾力を担うコラーゲンもすべてタンパク質です。実際には体内で数万種類が存在し、さまざまな役割を果たしています。
酵素、抗体、ホルモンもタンパク質の働きによるもの
たとえば、一番身近な仕事は「酵素」です。これは体内の化学反応を効率よく進める触媒としてはたらき、食べ物の消化やエネルギーの変換、デトックスなどに不可欠です。
さらに、身体を守る「抗体」や、体内の指令を伝える「ホルモン」の一部もタンパク質です。免疫がウイルスと戦うのも、ホルモンで疲労やストレスに対応するのも、多くはタンパク質の働きによるものです。
タンパク質は縁の下の力持ち
また、脳や神経の働きにも深く関係しています。タンパク質は神経伝達物質の生成に関与し、脳の成長や機能、さらに記憶や学習能力にも影響を与えます。つまり、タンパク質は体と心をつなぐ“ブリッジ”でもあります。
このように、タンパク質はただの材料ではなく、身体の仕組みを動かす“縁の下の力持ち”。健康な身体と心を維持するためには、常に良質なタンパク質が必要です。
毎日の補給とメンテナンスが重要
そしてもう一つ忘れてはならないのが、タンパク質は常に使われ続け、分解・再合成される“動的な栄養素”であるということです。筋肉や酵素といった構造体も、一度作れば終わりではなく、日々壊れては作り直される「ターンオーバー」を繰り返しています。つまり、タンパク質は摂って終わりではなく、毎日の食事で補給とメンテナンスをし続けることが重要なのです。

多様な働きで生命活動を支えるタンパク質
① カラダをつくる働き
【構造タンパク質】
筋肉、皮膚、内臓、髪の毛、爪、骨など、身体のさまざまな部分を作る材料になります。
◉細胞構成タンパク質
筋肉、皮膚、内臓など
◉コラーゲン
骨、皮膚、歯、爪、毛髪など
◉核酸タンパク質
DNA、RNA
不足すると→筋力の低下、骨が弱くなる、タンパク質合成能力の低下などから、ロコモやサルコペニアの原因に。
② カラダを動かす働き
【機能タンパク質】
体内で化学反応を促進し、物質の運搬、免疫機能の調節、細胞間のシグナル伝達などの役割を担います。
◉酵素タンパク質
酵素として代謝に関与します。
消化酵素(アミラーゼ、ペプシン、トリプシン)など
◉調節タンパク質
ホルモンが身体の機能を調整します。
血糖値を調整(インスリン)、成長促進(成長ホルモン)など
◉防御タンパク質
免疫にかかわり異物を排除します。
抗体(免疫グロブリン)、インターフェロン、リゾチームなど
◉輸送タンパク質
栄養物質や酸素の輸送を担います。
膜輸送タンパク質、酸素輸送(ヘモグロビン)など
その他、レセプターの構成成分として情報伝達にもかかわります。
不足すると→全身の代謝が悪くなり、身体の調節が聞かなくなり、細菌やウイルスに感染しやすくなるなど、老化や不調の原因に。
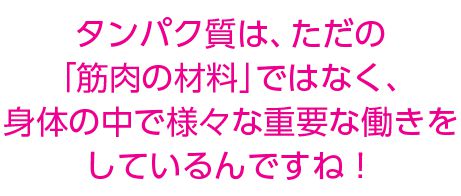
栄養書庫発行 : 『よくわかる健康サイエンス-11 タンパク質とアミノ酸と核酸』より